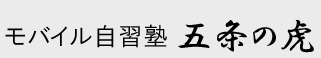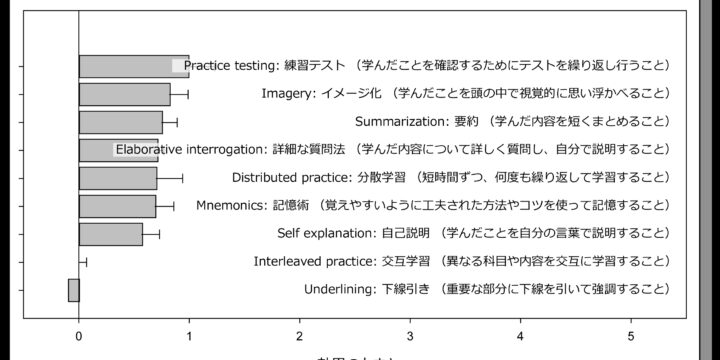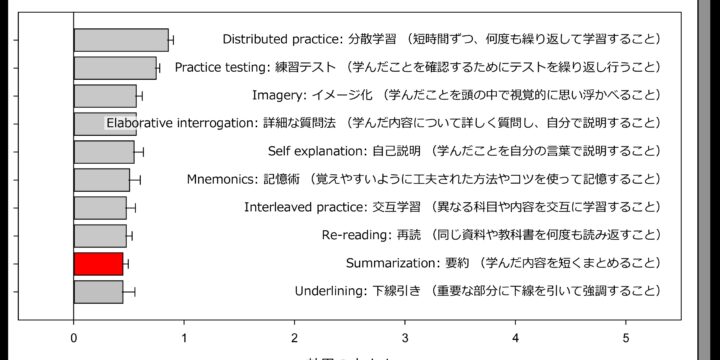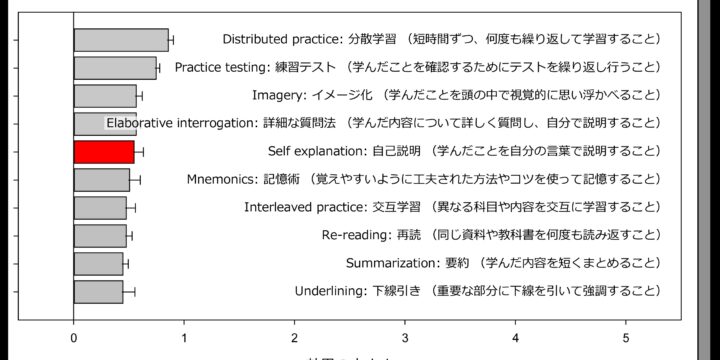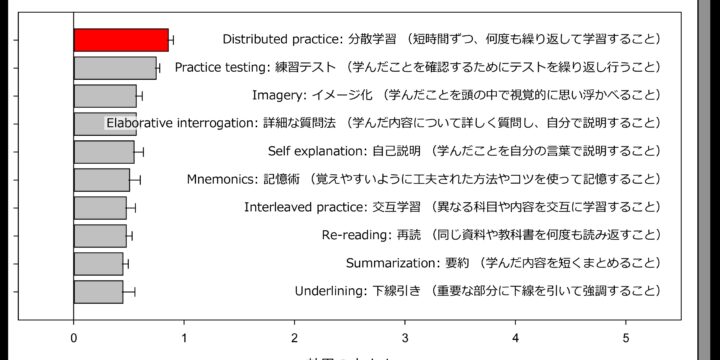Interleaved practiceとは
インターリービング学習とも呼ばれ、複数の異なるトピックやスキルを交互に学習することで、より効果的な学習結果を得るための勉強法です。具体的には、一つのトピックを集中して学習するのではなく、異なるトピックを織り交ぜながら学習することで、脳に様々な問題を解く練習をさせ、それぞれのトピックをより深く理解し、長期記憶に定着させる効果が期待できます。
例えば、英語学習であれば、単語、文法、読解といった異なるジャンルを一定の間隔で交互に学習することで、各ジャンルの理解を深めることができます。また、スポーツや音楽、イラストなど、他のスキル習得にも応用可能です。インターリービング学習は、学習内容の多様性を高めることで、脳の活性化を促し、学習効果を向上させるとされています。
この学習法の利点は、脳が退屈しないことにあります。同じトピックを長時間繰り返し学習すると、脳が退屈してしまい、集中力が低下する可能性があります。しかし、インターリービング学習では、異なるトピックを交互に学習することで、脳が常に新しい刺激を受け、集中力を維持しやすくなります。
また、インターリービング学習は、関連性のあるトピック間で行うことが重要です。例えば、英語の勉強と料理の勉強を交互に行うよりも、「歴史・世界史・現代社会」のように関連付けられる科目を交互に学習する方が、脳に定着しやすく、学習効果が高まります。
インターリービング学習は、特別なテクニックを必要とせず、誰でも簡単に始められる勉強法です。従来の反復学習で効果を感じられなかった方や、マンネリ化した学習方法を変えたい方に特にお勧めします。
インターリーピング学習として、一番効果を感じるものとしては数学の問題を解くときです。ある程度、力がついて来たけど、解き方が思いつかなった難しい問題でなんか解けそうだけど解けない問題はしばらく考えてわからなかったら、一週間ほど放置することです。しばらくすると、ふと解き方を思いつくことがあります。そのときは一気にその問題を解くわけです。このふと解き方を思いつく経験を繰り返すことで、実際の試験で最後にわからない問題の解き方を思いつく火事場のクソ力の源泉となるわけです。
それ以外にもいろんな科目を飛び飛びで勉強することで頭の中で整理する必要が出てきて、記憶に残りやすくなる効果が期待できます。